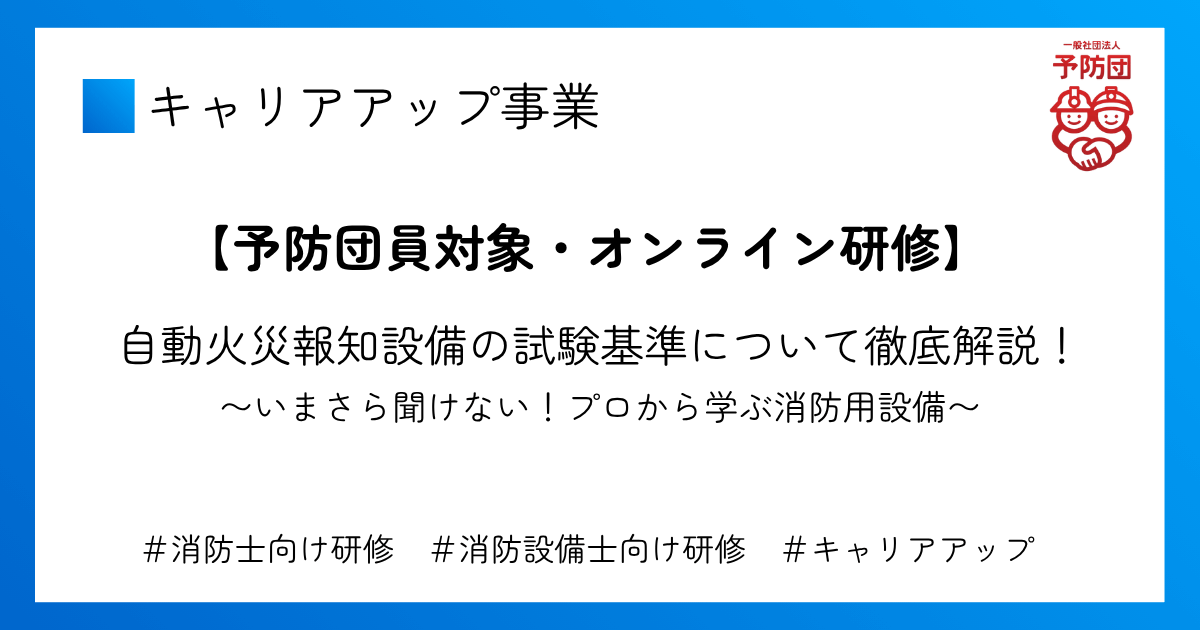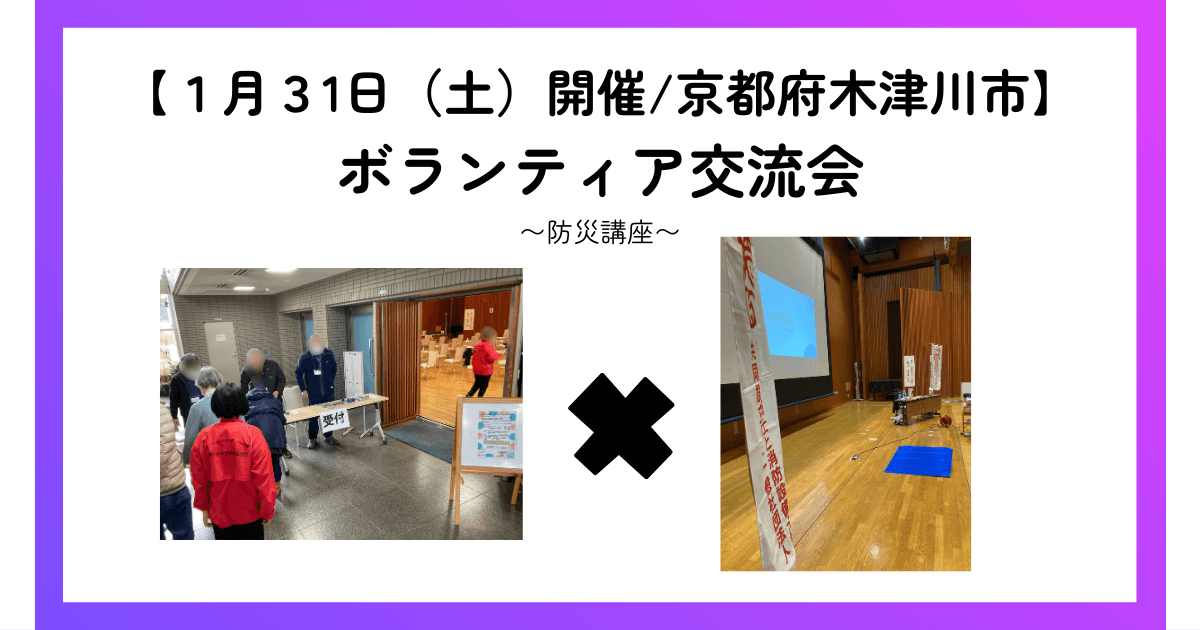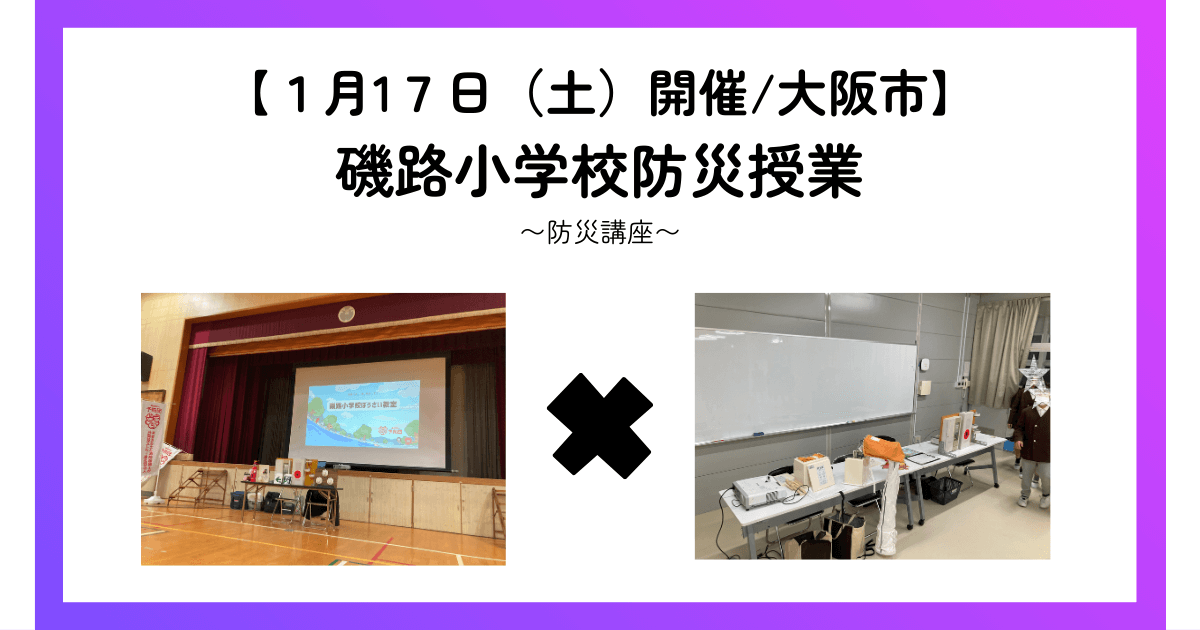先日予防業務を行う現役消防士や、現役消防設備士のメンバーを対象にした消防用設備オンライン研修会を開催し、自動火災報知設備の試験基準についての解説を行い知識のアップデートをしました。
今回このような研修会を実施させていただいた背景として、消防士も消防設備士も専門知識や技術を学びたいけど学べる機会や場所が少ない(または無い)という現状があり、どうにかできないかと模索していたところ、当法人のメンバーでもあり消防用設備に関わる教育事業を営んでいる合同会社Nワークス様に消防士や消防設備士向けに何か勉強会みたいなものができないかと相談させていただいたのがきっかけになります。
もちろん講師には「消防用設備の教育を支援する会社」をスローガンにしています合同会社Nワークスの代表 中島様にご担当いただき当研修会を実施しました。
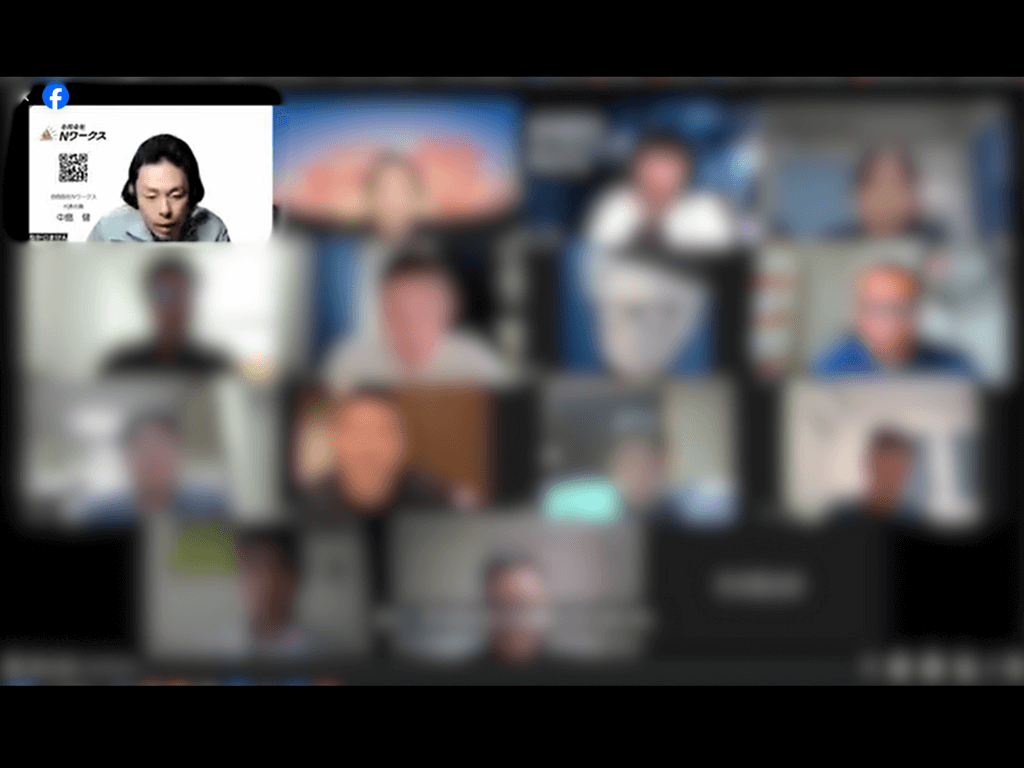
研修の内容は「自動火災報知設備及び配線の試験基準の解説」として
- 自動火災報知設備 試験基準
- 共通線試験及び送り配線試験
- 受信機 火災表示試験
- 回路導通試験
- 同時火災試験
参照:自動火災報知設備の試験基準(総務省消防庁)
- 配線 試験基準
- 開閉器と遮断器の違い
- 配線の工事方法
- 接地抵抗試験
- 絶縁抵抗試験
- 絶縁耐力試験
参照:配線の試験基準(総務省消防庁)
これらの内容を解説していただきましたが、中でも「共通線試験及び送り配線試験」における受信機のP型とR型といった機種によって取り扱いが異なるということや、「配線の工事方法」の部分に関しては参加者の皆様に「へぇーそうなんだ!」と、とても好評をいただきました。
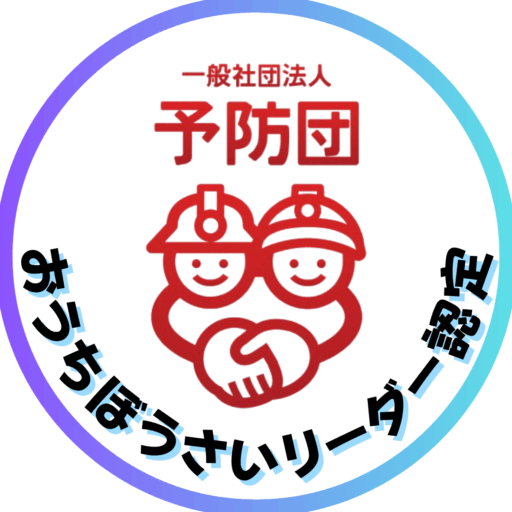
私たちが取り扱う消防用設備というものは誰でも簡単に扱えるものではなく、専門的な知識や技術、そして資格を必要とし、年々更新されていく消防法令に対応するために日々の研鑽をかかさず行いアップデートをしていかなければなりません。
例えば消火器の使い方1つにしても頭の中ではわかっているけれど実際にやったことがなければ、いざ!というときになかなかすばやく確実に使うことは難しいでしょう。
これも何回も訓練を行って取り扱い方法を熟知、体得しておかなければ実火災の時に有効に火災を消火できません。

このようにまずは私たち消防人(防火・防災に携わるすべての人の総称)が進んでアップデートを行ってそれを地域の方や一般の方に伝えることによって火災予防という事前対応と万が一の火災の時の速やかな消火・避難といった事後対応が行えるようになるので、まずは小さな一歩ではありますが有志が集まって勉強会を実施しました。
当法人では防災イベントの企画や運営、また今回の教育事業を通じて日本の火災予防に貢献するという使命がありますので、今後も各種イベントなどを通して少しでも火災予防に貢献できるように邁進してまいります。
予防団員になるためには?
一般社団法人予防団では、防災に関するオンライン研修や地域イベントの企画・運営、防災教育の普及活動を全国で展開しています。
さらに、現役消防士をはじめとする公務員のパラレルキャリア支援にも力を入れ、仲間とともに学び・実践し・社会に還元する仕組みづくりを進めています。
私たちは、**「防災を日常に」**を合言葉に、全国の消防人とともにより良い社会を築いていきます。
あなたもぜひ、予防団の一員としてこの輪に加わりませんか?🔥
気になる方はお問い合わせフォームから「予防団について教えて!」とコメントください💁♀️
オンラインミーティングの日にちを設定させていただきます。
最後までご一読いただきありがとうございました。